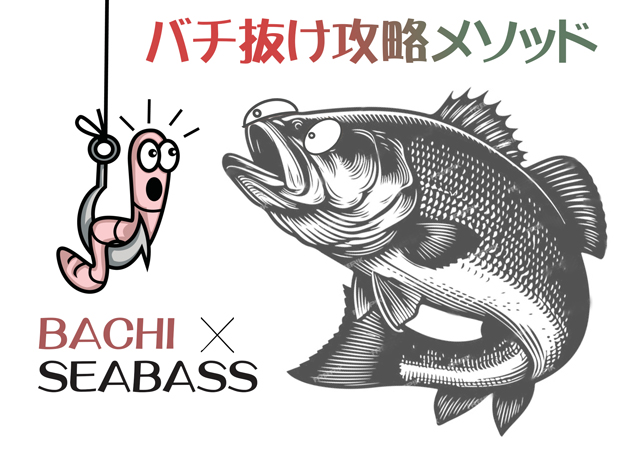バチ抜けの時期とこの頃に肝心となるパターンの攻略メソッドについて解説します。
基礎となるこの時期のバチの習性とシーバスの捕食行動などから、ポイントや釣りやすい時間帯をお伝えし、後半に3つの異なるバチ抜けのパターンの釣り方のキモになる部分を紐解いていきます。
バチ抜けとは?
バチとは、釣り具店などでもお馴染みのエサとしても使うイソメやゴカイなど環状生物のことを指しています。
いつもは砂や土の中に潜って生活している生き物ですが、産卵期になると底から抜けて水面付近まで浮上してきて流れに乗って群れで泳ぎながら生殖行動をしはじめます。このことをバチが底から抜ける=バチ抜けといいます。
釣りエサにもなるくらいの生物ですから魚が嫌いなはずもなく、大量に口にすることが出来る=簡単に捕食できるタイミングとなるため、特にその時々でいちばん捕食しやすいエサを選って食べるとい言われるシーバスには恰好のエサとなります。
シーバスはバチ抜けがはじまると、メインベイトと小魚を無視して、同時にほかの小魚がいるような混合ベイトの状況下でもバチを捕食することが多くなります。いわゆる偏食傾向になります。
バチ抜けの時期
このバチ類が抜ける産卵期が対象魚の釣りにとってバチ抜けの時期になります。
この時期は早いところでは2月の下旬から発生し、長いところでは梅雨入り前の6月くらいまで続く場所もあります。おおよそ3月~4月の春だと覚えておいて良いでしょう。
多少の時期のずれはあるものの、どの地域でも発生するので全国的に通用する釣りパターンのひとつです。
バチ抜けのポイント
バチ抜けのポイントはどこか見つけられれば、その場所に時合のタイミングでいけばハマりやすいパターンで、その場所はどこを探せばいいのか?というと
底が砂地、土の場所なら、その抜ける量やバチの種類(イソメかゴカイか、青か赤か)は違っていてもどこにでも居ますし、どこでも発生すると思っていていいです。
港湾部や河口でなくでも塩分濃度が濃い河川の中流域や街中の運河でも起きます。
また、バチはその場所で抜けて潮の流れに乗って流れていきます。そのバチを流れてくる方向に頭を向けてシーバスは待ち構えています。そのことを考慮してヒットポイントと立ち位置を見極めてトレースコースを頭にイメージしておくことも大事です。
一度場所が特定できたら、理由は定かではありませんが毎年同じ場所で抜けるので、そのポイントを把握しておくといいでしょう。
バチ抜けの時間帯と潮周り
場所が特定できていなくても、時期がはじまったら時間帯を絞って攻略していくとキャッチ率が高まります。
広いエリアで繁殖させようとする習性から流れに乗って広範囲を漂いながら生殖行動をします。この流れがあるとき=すなわち潮がよく動いている時合を狙います。
大潮の時がいちばんいいといわれますが、潮の周期で大潮が4日続くうちの大潮後半2日~中潮の4日間がもっとも有効です。
その潮周りで夕マズメが絡む夜間だとベストタイミング!
夕方日が暮れはじめる時間から潮が動き始め夜に潮止まりを迎える日が重なると絶好のバチ抜けの時間帯となります。
ただ時合は3~5時間続いて潮が動いてたとしても、そこにシーバスが着いていなければいけないわけでして、釣れる時間はその時間帯の中のほんの30分程度だった…なんてこともしばしばあります。
それがこの時期の釣りの難しいと言われる理由になっていると思います。
バチ抜けの3つのパターン
バチ抜けにも、その時々でいろんな状況が存在しそのシチュエーションごとに釣り方をアジャストしていかなければいけません。
バチにも種類があり、その場所で小さいバチしかいない場所、長い太いバチがたくさん居る場所などがあります。ルアーのカラーやサイズを変えて合わせていくといいでしょう。
バチパターン
水面を這うバチの大群が漂いながら流されている状態のこと。すでに水面まで浮いて来ている状態で視認性もよくアングラー自身が目視で確認できるいちばんいい状態です。光に対して集まってくる習性があるのでウェーディングなどで水面にライトを当ててみると一面に広がっているものが見えるかもしれません。
長さは10cm前後のバチがたくさんゆっくり身体を波打ちさせながらゆっくりと泳ぎ群れで漂っている状況です。
このような状況の場合は10cm前後の長さの細いシルエットのシンペンやシャローランナーで水面直下を攻略していきます。
底バチパターン
バチが抜けていても人間からは目視出来ない状況も存在します。浮いてきていなくても底に溜まっている状況です。
そのような場合、警戒心の強いシーバスは底でバチを捕食していることが往々にしてあります。人間からは水中の底付近は見えませんが、河川や河口で鵜やサギなどの水鳥らが水中に潜って何かを食べているような光景を目にしたらその辺り周辺の底でバチが抜けている可能性があります。
こういった時には底付近まで潜る重さのジグヘッドをでのワーミングか、サイズが小さめでローアピール系のバイブレーションが有効になります。
くるくるバチパターン
1cm~3cmほどの小さいバチ、いわゆるコバチがくるくると回転しながら泳いでいる状態です。抜けて表層に見えているものの一般的なバチ抜けルアーだと難しくてルアーセレクトが要になってくることが多いです。
釣れなくはないですが、10cm前後のプラグルアーよりも長さも5,6センチのしかも柔らかくて曲がるワームが最適だと僕は思っています。
バチパターンの釣り方
ここからはバチ抜けの基本的な釣り方と、3つのパターンごとの釣り方を細かに解説します。
【目次】
●バチパターンの釣り方の基本
基本はドリフト
レンジは〇〇をキープ
●くるくるバチパターンの釣り方は○○がキモ!
●底バチの釣り方
●バチパターンのタックルはここ○○が大事!
について1603文字でお伝えしています。